逆流性食道炎とは
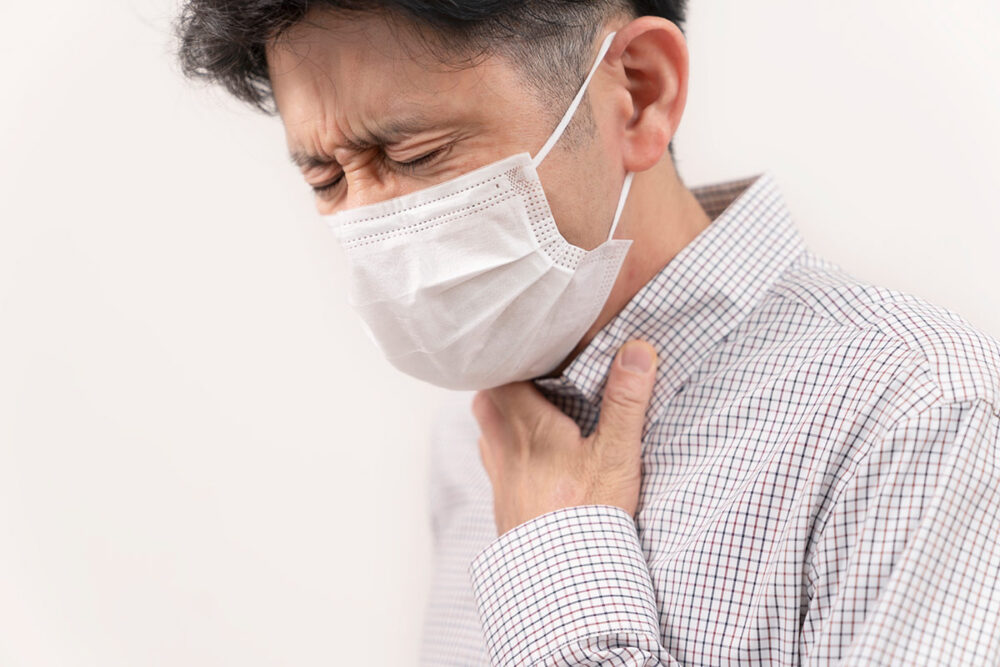 逆流性食道炎とは、胃の中にある強い酸性の消化液である「胃酸」が食道へ逆流し、粘膜に炎症を起こす病気です。胃酸は食べ物を分解するために不可欠な消化液ですが、胃の入り口にある下部食道括約筋という“逆流防止の役目”を担う筋肉が緩むことで、本来なら上がってこないはずの胃酸が、食道まで上がってしまいます。
逆流性食道炎とは、胃の中にある強い酸性の消化液である「胃酸」が食道へ逆流し、粘膜に炎症を起こす病気です。胃酸は食べ物を分解するために不可欠な消化液ですが、胃の入り口にある下部食道括約筋という“逆流防止の役目”を担う筋肉が緩むことで、本来なら上がってこないはずの胃酸が、食道まで上がってしまいます。
この状態が続くと、食道の粘膜は刺激により炎症を起こし、「胸やけ」「のどのつかえ感」「酸っぱい液がこみ上げる」などの症状が現れます。これらの症状が慢性的に起こる場合には、逆流性食道炎の可能性があります。
逆流性食道炎の原因
逆流性食道炎の背景には、日々の食生活や生活リズム、体質の変化が深く関わっています。以下のような要因が、発症のリスクを高めるとされています。
- 脂肪分の多い食事や刺激の強い食品の摂取
- アルコールやカフェイン飲料の過剰摂取
- 食後すぐに横になる習慣
- 肥満による腹圧の上昇
- 加齢や妊娠などによる体の構造変化
- ストレスや睡眠不足などの自律神経の乱れ
また、胃の手術を受けた後や、便秘が慢性化している方も腹圧の影響で胃酸の逆流が起こりやすくなります。
逆流性食道炎になりやすい人
以下のような方は逆流性食道炎を発症しやすい傾向があります。
- 食べる量が多く、早食いの方
- 脂っこい食事や甘い物が好きな方
- 飲酒や喫煙の習慣がある方
- 肥満気味の方、妊娠中の女性
- ストレスが強く、睡眠時間が不規則な方
年齢を重ねるにつれて筋力が衰え、下部食道括約筋の働きも弱まりやすくなります。高齢者の方にも多く見られる病気です。
逆流性食道炎の症状
逆流性食道炎の主な症状は以下のようなものです。
- 胸の奥が焼けるような不快感(胸やけ)
- 酸っぱい液体や苦味が喉まで上がってくる感じ(呑酸)
- のどの違和感、声のかすれ
- 食後や横になると咳き込みやすい
- みぞおちの痛み、胃もたれ
- 咳がでる(会話中や横になった時など)
これらの症状は風邪や気管支炎、胃もたれなどと似ており、自己判断では見落としやすいです。特に、長引く咳だけが症状として出る場合もあるので(逆流性食道炎による慢性咳嗽)、注意が必要です。
逆流性食道炎の検査・診断
 逆流性食道炎は、症状の問診が一番大事であり、疑わしい場合には、胃薬を処方して症状が改善するかどうか、「診断的治療」を行う場合もあります。必要に応じて胃内視鏡検査(胃カメラ)を行うことで、食道粘膜の炎症やただれの有無を直接確認する場合もあります。胃カメラが必要と判断される場合には、連携する医療機関を紹介いたします。
逆流性食道炎は、症状の問診が一番大事であり、疑わしい場合には、胃薬を処方して症状が改善するかどうか、「診断的治療」を行う場合もあります。必要に応じて胃内視鏡検査(胃カメラ)を行うことで、食道粘膜の炎症やただれの有無を直接確認する場合もあります。胃カメラが必要と判断される場合には、連携する医療機関を紹介いたします。
また、内視鏡で異常が見つからなくても、症状が典型的であれば「非びらん性逆流症(NERD)」と診断されます。この場合においても治療の対象になります。
逆流性食道炎の治療
逆流性食道炎の治療は、「生活習慣の見直し」と「薬による胃酸のコントロール」が基本となります。
生活習慣で意識したいこと
- 食後2~3時間は横にならず、できるだけ体を起こして過ごす
- 睡眠時は上半身をやや高くする(枕を高めに)
- 脂っこい料理や刺激物(香辛料、柑橘類など)を控える
- 禁煙・節酒、適度な運動を継続する
- 規則正しい生活リズムと十分な睡眠の確保
これらを意識することで、胃酸の逆流を防ぐ環境を整えることが期待できます。
薬物療法のポイント
医師の判断により、以下のような薬が使用されます。
|
治療のしくみ |
主な薬の種類 |
代表的な薬剤名 |
特徴・ポイント |
|---|---|---|---|
|
胃酸の分泌を強力に抑える |
プロトンポンプ阻害薬(PPI) |
ネキシウム(エソメプラゾール)、タケプロン(ランソプラゾール)、パリエット(ラベプラゾール) |
逆流性食道炎の第一選択薬。長期使用に注意。 |
|
さらに強力に抑える |
カリウムイオン競合型酸分泌抑制薬(P-CAB) |
ボノプラザン(タケキャブ) |
PPIよりも即効性・効果が強い。近年の主流。 |
|
胃の動きを改善する |
消化管運動促進薬 |
ガスモチン(モサプリド)、プリンペラン(メトクロプラミド) |
胃からの逆流を防ぐ補助的な薬。 |
|
胃粘膜を保護する |
粘膜保護薬 |
アルロイドG、セルベックス(テプレノン) |
粘膜の修復をサポート。補助的に使用。 |
薬の使用期間や種類は、症状の重さや改善状況に応じて変わってきます。自己判断での中断は避け、医師と相談しながら継続することが大切になってきます。
まとめ
逆流性食道炎は、日々の生活と密接に関わる病気です。「最近、胸やけが気になる」「夜間の咳が続く」「胃の不快感がとれない」などの症状が見られたら、ぜひ一度相談してみてください。
逆流性食道炎に関するよくある質問
逆流性食道炎は自然に治ることはありますか?
軽症の場合は生活習慣の改善で症状が和らぐこともあります。ただし、胃酸の逆流が続くと慢性化しやすいため、症状が続く場合には受診をおすすめします。
胸やけ以外にも逆流性食道炎の症状はありますか?
胸やけ以外に、喉の違和感、慢性的な咳、声のかすれ、胃もたれなどが 逆流性食道炎による症状のこともあります。
逆流性食道炎で、咳だけしか症状がない場合もありますか?







